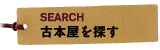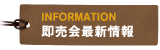- 大震災が我が国を襲ったあの日、東京古書会館では普段通り活気ある交換会が開催され、地下即売展会場も一般のお客様で賑わっていました。昭和23年の東京古書組合発足以来、経験したことのない立て続けに起こる強く激しい揺れに慄然としました。交通機関はストップし、組合員及び職員の約三十名が古書会館に宿泊することになりましたが、このような事態になることを想定していなかったために、食料などの準備が整っていませんでした。今後は同様のケースにも対応できるような会館機能を構築しなければならないと切に感じた次第です。
被害の甚だしい東北地方の組合員とはなかなか連絡が取れず、大変憂慮しました。特に宮城組合の方々とはしばらく電話もつながらず、一週間ほど経ってようやく組合長さんと話すことができましたが、ある組合員の店舗が津波に流されてしまったという痛切な報告を受けました。その他、本が散乱した、棚が倒壊したというようなことは聞きましたが、店舗の崩壊などの致命的な被害はなかったとのことでした。福島や青森でも程度の差はありますが、やはり同じような状況で、中には店舗に戻ることができず避難生活を余儀なくされている組合員もいるということです。 関東地方の被害も少なくありませんでした。震源地に近い北関東はもとより、東京でも崩れた本の整理に忙殺され、三週間以上営業ができなかったり、棚が根こそぎ倒壊してしまったために、在庫をすべて交換会に出品せざるを得なくなった組合員もいました。特に棚が倒れたという報告は相当数受けています。お客様の安全を守る上でも、今回のような未曾有の震災が起きた場合であっても、その被害を最小限に食い止められるような工夫を各組合員レベルで行わなければなりません。
東京古書組合が運営している古書販売サイト「日本の古本屋」も打撃を受け、三月は受注件数・金額ともに約三割減少しました。震災被害の大きかった東北六県や茨城県はもちろん、全国的に落ち込みました。店舗販売も芳しくなく、本の街・神保町でさえ震災以前に比べると人通りがだいぶ少なくなったような気がします。流通が一時的に停まったことも大きいでしょうが、何より今回の震災は人々の心から本を読む余裕を奪ってしまった―「自粛」という言葉に代表されるように、文化や娯楽を楽しむことがそのまま罪の意識につながってしまう、そのような価値観が根付いてしまった。被災地の現状を鑑みれば、当然私たち個人が慎みをもって生活しなければなりません。けれども、あまりにもその傾向が強固なものになれば、文化そのものが停滞していくのではないか……。
そのような懸念を抱き、古本屋の行く末に不安を覚えていた最中、海外の古書業界から励ましの言葉を頂きました。ニュージーランド・豪州古書店連盟のサリー・バートン会長や英国の古書組合からはお見舞いのメッセージを、そしてABAというアメリカの古書組合からは被害の大きかった古書店に直接義援金を送りたいという大変ありがたい提案を受けました。被害の程度を区別することは困難ですから、赤十字社へ寄付してもらうことをお願い致しましたが、国は違っても、同業者としての温かい心遣いに感激しました。そして私たちはその気持ちに必ず応えなければならないと感じました。 国を挙げてこの苦難を乗り越えようとしている今、我々古書組合も微力ながら震災復興の一助となるべく、四月十三日に名古屋で開催された全古書連総会において、各組合で集めた義援金を全古書連本部の東京組合がとりまとめ、日本赤十字社へ寄付することに決定しました。また既に各組合単位でも独自に様々な形で寄付などの活動を行っています。
しかし私たち古本屋の仕事は、本を必要としている人たちのところへ本を届けること、そして何よりも本の価値を守り抜いていくことです。 震災以降、お客さんから本を買い取って欲しいという問い合わせが沢山届くようになりました。物質としての本に対する恐怖感が芽生えてしまったこともあるでしょうし、先程述べたような読書に対する意欲が失われてしまったことも大きいでしょう。原発の問題もありますが、何かしら社会的な安定感がもたらされなければ、このような状況はなかなか変わらないでしょう。
けれども、本というのは本来的に心の安逸を与えるものであり、現実とは異なった方向へ想像力を伸ばしてくれます。そして最も重要なことは、本には様々な危機を乗り越え、歴史を織りなしてきた先人達の知識が詰まっているということです。 今この時、日本の前に立ちはだかっている壁は途方もなく高いものですが、それを乗り越えた未来に、世界がまだ成し遂げたことのない新しい社会を作ることができるはずです。そのためにこそ、我々が扱っている古書に記されている情報が様々な局面において活用されるべきではないかと私は強く思うのです。