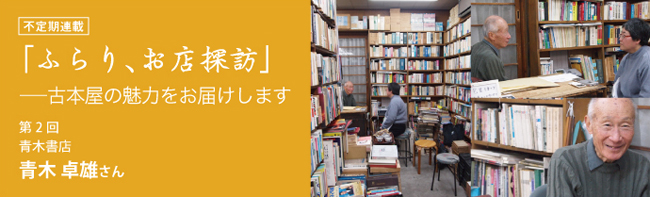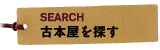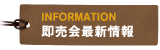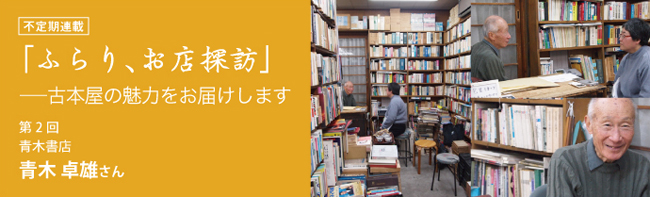
聞き手 西平守次 (球陽書房)
聞き手 五本木広子(苔花堂書店)
-
- 青木さんといえば、総会後の懇親会で挨拶されている穏やかな姿しか存じませんでしたが、ある方は口を揃えて「こんな穏やかじゃなかった」と言います。「もっとツンツンした感じだった」と。青木さんに尋ねてみても「そう?」と言うばかり。ご自身が考えるほどのんびりとはしていなかったということ?。
「悔いがない」ときっぱり言い切る姿勢そのものが一番うらやましい。
店頭には均一本、店の入口近くには読み物があり、だんだん奥に行くにつれて力を入れているジャンルになる。中央線沿線の本屋は土地柄もあるのでしょうが、このスタイルが多く、文化的存在としての「古本屋」というイメージを作りつつ、幅広い層に「本の世界」に入ってもらえる店作りのように思えます。「自給自足で」、とおっしゃる方は一様に「少し恥ずかしいですが・・・」というニュアンスを湛えますが、自分の店の構成をお客さんからの買取でまかなうというのは誇っていいように思います。お客さんの多くは店の品揃えや雰囲気、なによりご主人その人をみて、ここの店に本を売ろう、と思う。店の棚そのものが一番のアピール、一番の買い入れ広告、それをすべて自前の店で行っている。
失礼を承知で申し上げると、もう青木さんのお店は「活きのいいお店」とは言いにくいかもしれません。でも、エアコンではなく石油ストーブのぽかぽかと暖かい店に、おずおずと入ってきて本を見回して買っていく若者や、「これ明日取りにくるから、とっておいて」と本を預ける買い物帰りのおばあさん。こんなふうに毎日お店にくる人の中には、青木さんが意識しないところで、「青木書店があって良かった」と思った人が少なからずいたことでしょう。お客さん自身がそこで何かを見つけていく。それが、昔も今も変わらぬ町の古本屋の姿に思えます。
(苔花堂書店 五本木広子)