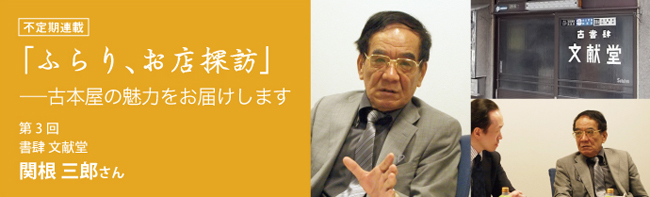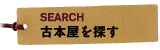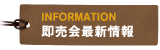聞き手 矢下晃人 (アルカディア書房)
聞き手 宮部隼人 (古書 Dejavu)
- 宮部
- 文生書院さんの仕事を手伝始められたのは何歳頃の事でしょうか。
- 関根
- 高校生になってからだよ。元々文生書院は仲御徒町にあったんだけど、近くに変電所があって空襲で類焼する危険があるからと、昭和十九年に強制的に立ち退かされたんだ。商売はオヤジさん一人でやっていて、そのうち秀雄氏が働くようになり、僕も「一緒にやらないか」とスカウトされた。本屋といっても普通のしもた屋で、玄関や廊下に本がそのまま積んであった。目録も当然ガリ版、その機械も昭和六十年ぐらいまで残っていたな。お客さんはほとんど学者だった。
初めは自転車も無かったから、大きい風呂敷をいくつも抱えて本を運ぶのが本当にきつくて。近くの商店から大八車を借りることもあったけど、荷物を載せていなくても重いし本郷はどこへ行っても坂だらけだからね。三人で必死になって押したこともあったよ。秀雄氏の同級生の森長炭店さんがリヤカーを持っていて「あれを借りれたら楽なのになあ」と思っていたんだけど、いつも使っていたから、代わりに自転車を貸してもらうこともあった。
その後文生書院でもやっと二台の自転車が購入出来てからは大変で、都下の立川辺り迄一日がかりで買入品を運んだりもした。
地方へ買入に行くときは本を八百屋さんでリンゴ箱を買って詰めて送るんだけど、譲ってもらえる八百屋さんを探すのも一苦労だったね。
- 宮部
- 当時はどの様に地方客へ買い入れの宣伝を行っていたのですか。
- 関根
- オヤジさんが人名録なんかを見て買入の葉書を送っていたんだ。
- 宮部
- その後、当時かなり高価なオートバイを導入されたとのことですが、いつ頃のことですか。
- 関根
- 昭和三十年代後半じゃないかな。今東部にいる鵜沢さん(ウザワ書店さん)が外神田の押田モータースと言うオートバイ屋に勤めていて、その伝手で最初に買ったのがシルバーピジョンのスクーター。中古だったし、重たい本を乗せているからタイヤがすぐパンクして大変だったよ。
- 宮部
- 関根さんがお店で最初に免許を取られたのですか。
- 関根
- いや、確かそのスクーターの前にも自転車にエンジンが付いただけの、いわゆる「原動機付き自転車」(自転車の後輪に取り付ける、現在のラジカセのスピーカー程のサイズでゴムを部品の一部に使った「カブ」と言う名称の小型のエンジンが、当時の価格で一〜二万円程度でバイク店等で販売されていた。自転車店で簡単に取付工事が出来た。)があったから、先に誰か取っていたんじゃないかな。僕は十六歳の時に小型自動車免許(後に普通自動車免許へ統合)を取ったんだけど、当時は試験も楽でね。自動車教習所で学科をやって、外をくるっと一周すればそれでおしまい。なにせ車なんか全然走ってない時代だからね。「ウソでしょ」って言われるけど、東大の正門前で野球の三角ベースができたくらいだったから。
- 宮部
- 文生書院さんに勤務されていた頃の印象に残っていることをお聞かせください。
- 関根
- 三十年以上勤めたんだけど、その間に大きなブームが二回あった。一回目は昭和三十年代の中共貿易が盛んな頃で、極端に言えばどんな本でも売れた。一万ポンドのLC(レターオブクレジット)がいきなり送られてきて、一応ジャンルは指定するんだけど、基本的には何でも良いから本を買えるだけ送ってくれと言ってくる。理工系が多かったけど、あの頃本郷でバックナンバーを専門に扱っていた稔書房さんや塚田書店さんなんかも相当潤っただろうね。そうやって集められた大量の本がトラックに積み込まれて梱包業者か、あるいは大安文化貿易とか極東書店とかタトル商会みたいな代理店へ運ばれていくんだ。今振り返れば「あんなもの売っても良かったのかな」って思うけどね(笑)。
- 宮部
- 日中国交正常化のかなり前になりますが、当時の中国のエリート層は日本語を習得し、日本語の学術書で勉強していたのですね。
- 関根
- 満鉄の膨大な資料などを初めとして、戦後ソ連が回収していった事なども有って、中国には文献が無かったと思う。 それからもう一つ大きかったのは、昭和四十年代後半からの大学新設や昇格、特に医科大学が全国各地で設立された頃は本当に忙しかったね。東京にはほとんど居なかったし、四十週以上休みが無いこともあった。というのも大学の先生たちは自分の専門しか知らなくて、全般的な資料をまるで把握していないから、こっちが一から調べて用意しなきゃいけなかった。しかも地方だと駅から遠かったり、まだ道も整備されていなかったりして骨が折れたよ。