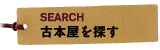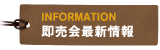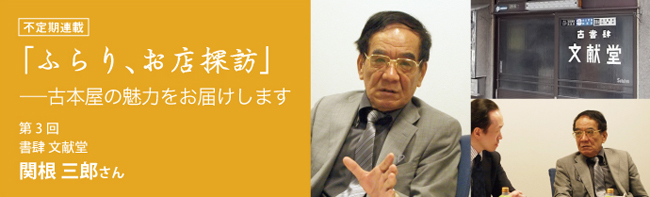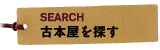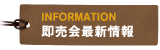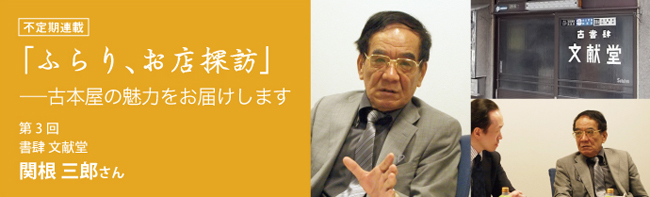
聞き手 矢下晃人 (アルカディア書房)
聞き手 宮部隼人 (古書 Dejavu)
- 宮部
- 昭和四六年まで、文京支部で運営されていた古書の業者市の支部市(赤門会)のことをお聞かせください。
- 関根
- 僕も手伝いで出入りしていたけど、戦後間もない頃は後に「文伸堂」っていう文房具屋になった場所で行われていたんだ。それから湯島の道具会館へ移った(※昭和二十四年・『組合五十年史』)。せいぜい二十人いるかというぐらいで荷物も自転車やバイクで持ってきていたからそれほど多くなかった。主に秀雄氏が買入をやっていて、僕はサポートしていただけなんだけど、経営員(仕分けや陳列、入札の開札など実際に市の運営を行う係。)も今の体制とは違っていたし、最初は振り(市への参加者が声を上げて競り落とす方式の市。所謂セリ方式。)だけだったから相場も今よりはずっと覚えやすかったよ。
交換会が赤門会という名前になって、振りから置入札(古本の束に付けられた封筒に業者が入札価格を書き込んだ用紙を入れ、最も高い値を書き込んだ業者が落札する仕組。)になり(※当初は半年間の試験導入。大市(年に一回開催される大規模な市。)では振りも併用。昭和三十八年・前出)、会場も道具会館から本部へと移った。(※昭和四十年頃。洋書会(「東京洋書会」東京古書会館にて毎週火曜日開催されている洋書中心の市。)開催日の午前中を赤門会が利用することに・前出)それから本部会館が建設されたりしているうちに資料会(「東京資料会」東京古書会館にて毎週水曜日開催されている学術書、学術資料中心の市。)との合併が持ち上がってくる。元々扱っている品物も似通っているしメンバーもほとんど同じだから、一つになった方が色々と好都合な面はあったんだよね。ちなみに昔の資料会は曜日制ではなく八の日(八・十八・二十八)開催で、荷物が多ければ日付が変わるぐらいまで時間がかかっていたんだ。
古典会(「東京古典会」東京古書会館にて毎週火曜日開催されている古典籍中心の市。)みたいに廻し入札(机の前に着席した業者へ古書を順番に廻して、入札を行う方式。)だったからね。入札のスピードが遅い人のところに本が山になっちゃって。典型的なのはうちのオヤジさんなんだけどさ(笑)。二代目の会館でローラーを使うようになってからは大分早くなったんだけど、荷物を動かしながらの入札はやっぱり大変だよね。今は大量の荷物が来ても捌けるでしょう。前会館の立替の時利用した、日貿会館時代はワンフロアで荷捌き場も物凄く狭くて大変だった。今はこの様な立派な部屋(役員室)も出来て会館も広くなったし隔世の感が有りますね。
- 宮部
- 同業の皆様とはどの様なお付き合いをされていたのでしょうか。
- 関根
- 昭和四十年代に資料会のメンバーで「新人会」というのを作って、年に一、二回は旅行したね。いつも僕がツアーコンダクターになって大体二泊三日、全国を隈無く回ったよ。同じ頃に本郷と神田の十数名で「本神会」を立ち上げて、やっぱり色々なところへ遊びに行った。それからこの二つの会が合同で毎年必ずスキーへ行く。多いときには十数家族、四十人以上になったこともあったよ。だけど中には全くスキーをやらない人もいて、一日中将棋を指しているんだよ。民宿へ着くとそこの店主が「将棋指しが来たぞ」ってすぐ村へ知らせに行く、すると将棋好きがぞろぞろやってくるんだ(笑)。